近年、住宅の省エネ性能に注目が集まり、「断熱等級6」や「断熱等級7」といった新しい基準が話題になっています。私は数年前から「夏も冬も快適で、光熱費を抑えられる家を建てたい」という思いがあったので、この“新しい断熱等級”に興味を持つようになりました。
しかし、いざ調べてみると「断熱等級6って具体的にどれだけ違うの?」「UA値0.38W/㎡Kなんて言われてもピンとこない…」と、初心者には分かりにくい専門用語がずらり。
本記事では、UA値0.38W/㎡Kというハイスペックな断熱性能を持つ、我が家の“リアルな住み心地”をお伝えします。
「高気密・高断熱にこだわると費用が高いんじゃない?」と心配している方や、「南向きの大開口を付けたら暑くなる?」「第一種換気って何?」という方に向けて、
実際の体験談+数字を交えてお話ししますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
【本題①】わが家の基本情報:鉄骨造・35坪・断熱等級6・高気密など

実際の暮らし心地を語る前に、まずは「わが家の仕様」をご紹介します。家のスペックを把握していただくことで、よりイメージが湧きやすくなるはずです。
• 構造:鉄骨二階建て
• 延床面積:35坪(約115.7㎡)
• 断熱性能:断熱等級6(UA値0.38W/㎡K)
• 気密性能:高気密仕様(C値1.0前後)
• 換気方式:第一種換気システム
• 冷暖房:個別エアコン(各部屋に設置)
• 窓の向き:南向きに大開口を配置
なぜ鉄骨造を選んだか?
よく「木造の方が断熱を高めやすいし、コストも安い」と言われますが、私たちは以下の理由で鉄骨造を選びました。
1. 間取りの自由度
鉄骨造だと強度が高いため、大きな窓や吹き抜けを作りやすいです。我が家は南向きに大開口窓を設けて、光をたっぷり取り入れたかったので鉄骨住宅を選択しました。(吹き抜けはデメリットが多いので採用はしていません)
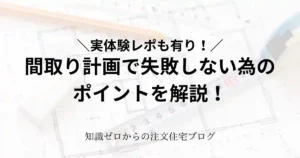
2. 耐震性や耐久性
地震大国の日本。永く住む家だからこそ、鉄骨ならではの安心感が魅力でした。
とはいえ、鉄骨造で断熱等級6レベルのスペックを実現するのは、木造以上に追加コストがかかりやすいというデメリットもあります。このあたりは、実際にハウスメーカーや工務店を比較して分かったことでもあります。
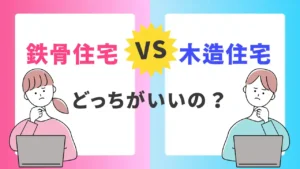
【本題②】実際の暮らし心地・快適性:夏と冬でどこまで変わるの?

「せっかく高断熱・高気密にお金をかけても、実際は快適じゃなかったら意味がない…」という不安、ありますよね。私自身も「本当に断熱等級6は必要なのかな?」と疑問を抱いていました。ですが、住んでみると、想像以上に季節ごとの快適さが違うと実感しています。
夏:南向き大開口って暑くない?
真夏の直射日光が差し込むと、室内が暑くなるのでは?と心配される方は多いでしょう。わが家の場合、軒の出(壁から700mm程度の長さ)をしっかり設計に組み込んだので、思ったほど部屋の温度は上がりません。エアコンの使用時間は日中30分ほどで、リビングを25〜27℃程度に保てています。
もちろん、南向きの大開口は日射が多く入るため、夏の午前中や夕方は少し室温が上がりがち。でも、太陽の高度が高い時間帯は軒が日差しを遮ってくれるので、「暑くて耐えられない!」なんてことはなく、むしろ自然光が心地よい空間になっています。
冬:足元からジワっと暖かい、冷えにくい家
冬場、床付近が冷えるのは高気密・高断熱住宅でも起こりがちですが、わが家では第一種換気を採用し、外気との温度差を熱交換で和らげているため、廊下に出てもヒヤッとしにくいと感じます。個別エアコンは部屋ごとに付けていますが、リビングのエアコンを弱運転すれば十分。暖房を切って数時間経っても、室温が急激に下がることはあまりありません。
また、鉄骨だから結露しやすいのでは?という懸念もあったのですが、高断熱の窓サッシ&換気システムのおかげで、今のところ窓ガラスがビッショリになるほどの結露は見られません。
【本題③】建築費・維持費はどのくらい?コスト面のリアル
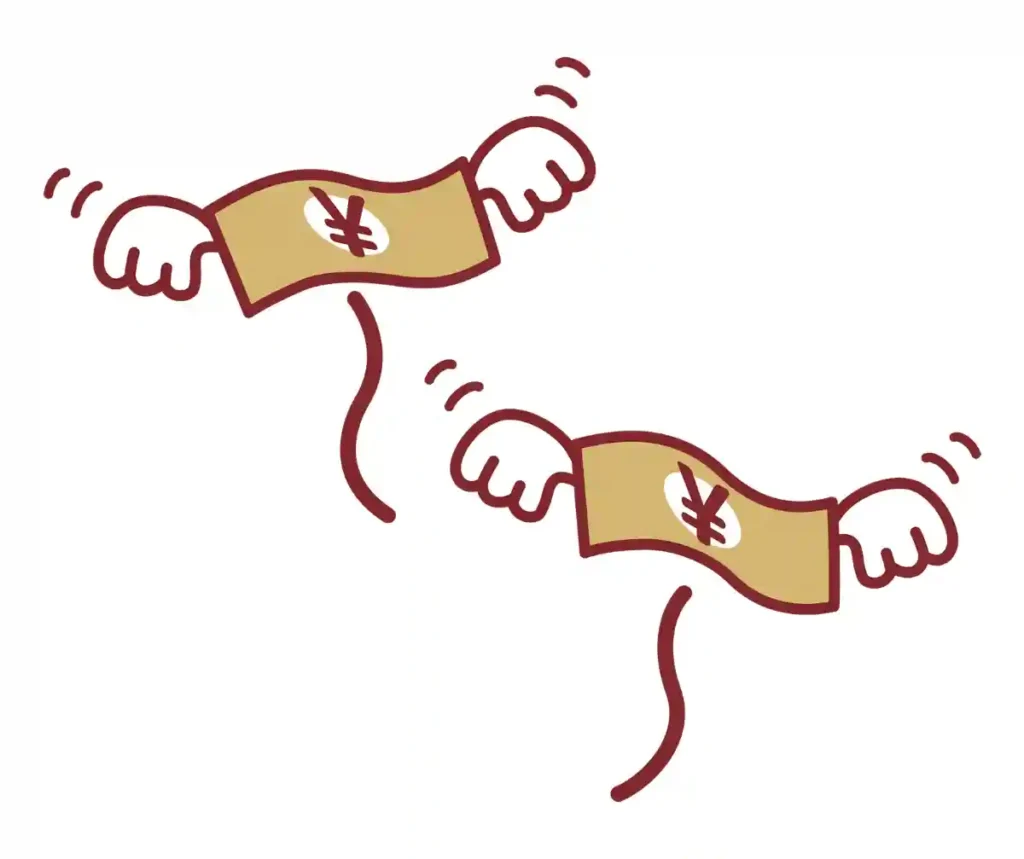
「高断熱・高気密にすると費用がかなり上乗せされるって聞いたけど、本当?」と疑問に思う方も多いでしょう。私の場合は、標準仕様(断熱等級4)に比べて、250〜300万円ほど追加コストが発生しました。理由は以下の通りです。
- 断熱材のグレードアップ:外壁・屋根により厚みのある高性能断熱材を採用
- 樹脂窓サッシ & Low-E複層ガラス:アルミ樹脂複合よりもさらに断熱性能を高める窓に変更
- 第一種換気システムの導入:熱交換率の高いユニットを取り入れたため、設備費がやや高め
光熱費は実際どのくらい変わったのか
以前住んでいた賃貸(鉄骨住宅)では、夏はエアコンをほぼつけっぱなし、冬はエアコンとこたつを併用して電気+ガスで月2.5万円近くになっていたこともありました。
それが今では、電気代+ガス代合わせて1.5万円程度に収まっています。季節によって変動はありますが、トータルで月1万円ほど節約できた感覚です。
もちろん「断熱性能がもっと低くても充分」という考え方もありますが、長期的に見ると断熱性能を上げた分、快適さと節約効果が得られるという点が大きな魅力でした。
【体験談】苦労したポイント&成功のポイント

家づくりは“やりたいこと”がどんどん増えていく反面、それを実現するためには設計の工夫やコストのバランスを取らねばなりません。私が苦労したのは、次の2点です。
1. 換気システムの配管ルート
• 第一種換気を採用すると、天井裏や小屋裏にダクトを通す必要があり、どこに配管スペースを設けるかに頭を悩ませました。
• 施工が終わってしまうと大がかりな変更が難しいため、設計段階から配管図を細かくチェックすることが大切だと実感しました。
2. 日射取得と遮熱のバランス
• 南向きの窓を大きく取りたい反面、夏の暑さが気になる…。
• 外付けブラインド、軒の出、庇、植栽など、複合的に対策して「明るさ」と「遮熱」を両立させました。
一方で、導入して正解だったと思うのは、
個別エアコンの採用です。
全館空調も検討しましたが、維持費やメンテナンスの手間を考えると、部屋ごとにエアコンを設置して必要なときだけ冷暖房する方が合っていました。加えて、故障リスクが一台に集中しないのも地味に安心ポイントでしたね。
無料間取り作成サービスを利用してみよう
ここまで読んで、「断熱等級6の家、なんとなく良さそうだけど、うちの条件でも実現できる?」と思われた方は、無料間取り作成サービスを使ってみるのがおすすめです。建築のプロに自分のライフスタイルや希望を伝えると、断熱性能や換気方式を考慮した設計を提案してもらえます。
- たとえば、「UA値0.38に近づけるにはどのくらい追加費用がかかるのか?」「鉄骨ではなく木造で同じ性能を出せるか?」といった具体的な疑問にも、プロがアドバイスしてくれます。
- 間取り図と一緒に大まかなコスト概算も出してくれるケースが多いので、比較検討がしやすいのが魅力です。
【PR】タウンライフ
ハウスメーカー・工務店の一括見積もりで比較するメリット
「じゃあ、どの会社に頼むべきなの?」という疑問は多くの方が抱えます。私自身も最初は大手ハウスメーカー数社を回り、工務店の比較もしたのですが、それだけだと“適正価格”や“本当に信頼できる施工”が判断しづらい面がありました。
そこで活用したのが一括見積もりサイト。複数のハウスメーカーや工務店から同時にプランと見積もりを取り寄せることで、
- 費用差や施工実績を比較できる
- 会社ごとの得意分野(鉄骨・木造・高断熱・デザイン性など)が見えてくる
- “本当の意味での費用対効果”が分かる
このおかげで、あやうく割高な契約を結ぶところだったのを回避できた実感があります。断熱性能や換気方式といった専門的な仕様についても、何社かに提案を受けると違いがはっきりして面白いですよ。
【PR】タウンライフ
【まとめ】断熱等級6で得られる快適性を実感しよう
最後に、断熱等級6住宅の魅力を改めてまとめます。
- 夏は日射対策+高気密・高断熱で、エアコンの使用時間が短く済む
- 冬は暖房を一度入れれば冷めにくいので、部屋間の温度差が小さい
- 光熱費が以前に比べて月1万円ほど節約できている
- 施工費は標準仕様よりも+250〜300万円ほど上乗せになったが、長期的に見ると快適性&ランニングコストのメリットが大きい
家づくりは大きな決断ですが、情報収集をしっかりして納得のいく住宅性能を選ぶと、後悔が少なくなるはずです。特に、断熱性能と換気は毎日の暮らしや光熱費に直結する部分なので、時間をかけて検討する価値があります。
今すぐできる2つの行動
【PR】タウンライフ
• 希望の断熱性能&換気方式を盛り込んだ間取りを提案してもらおう
• 複数社のプランを比較し、本当に納得できる家づくりをスタート
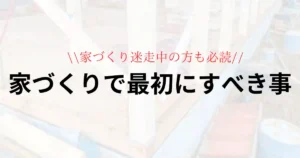
「断熱等級6 快適性 実体験」というキーワードが気になる方は、ぜひこうした無料サービスをフル活用してみてください。きっと、自分の理想に近い家やコストを抑える方法が見つかるはずです。
- 本記事で紹介している数値(UA値や光熱費、追加コストなど)はあくまで「私の家の場合」です。地域や家族構成、建設会社の違いによって結果は変わるので、参考程度にご覧ください。
- 価格や性能は日々進化しているため、最新情報は必ずハウスメーカーや工務店の担当者へ確認をお願いします。
- 各リンクは提携先への誘導を想定しており、詳細な利用条件やキャンペーン内容は各サイトでご確認ください。
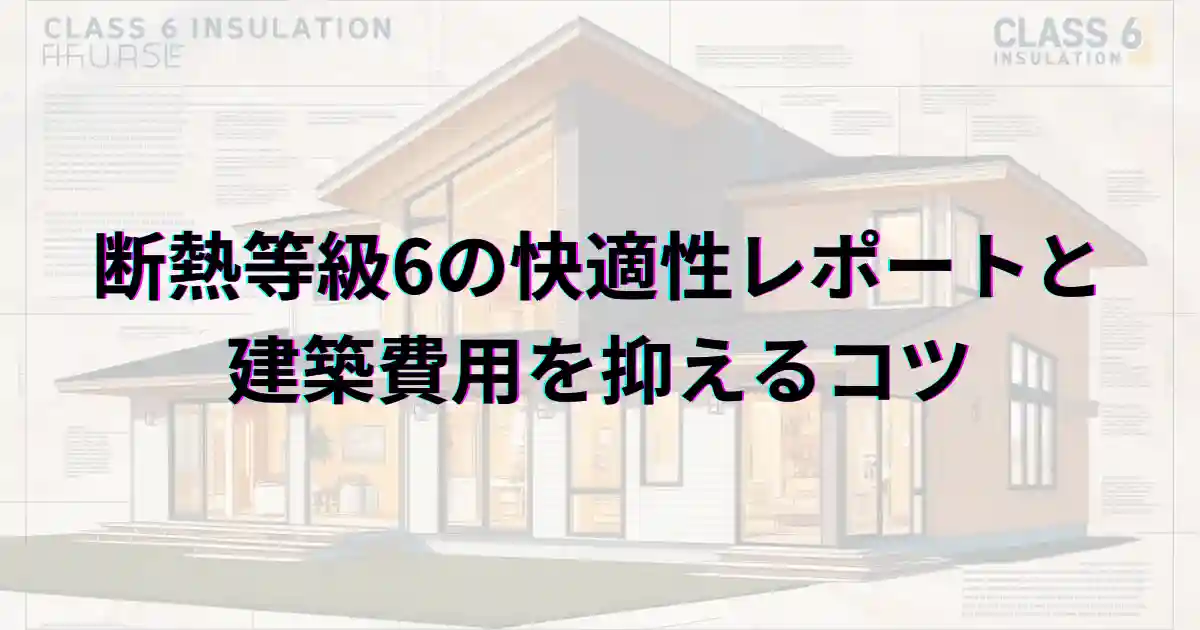
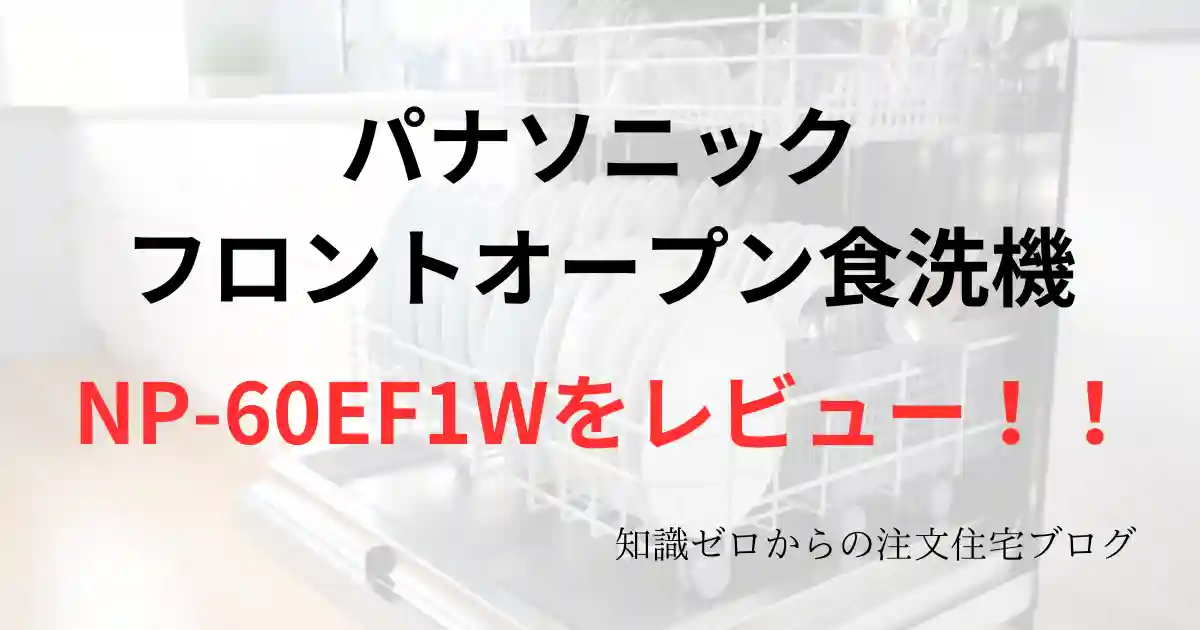
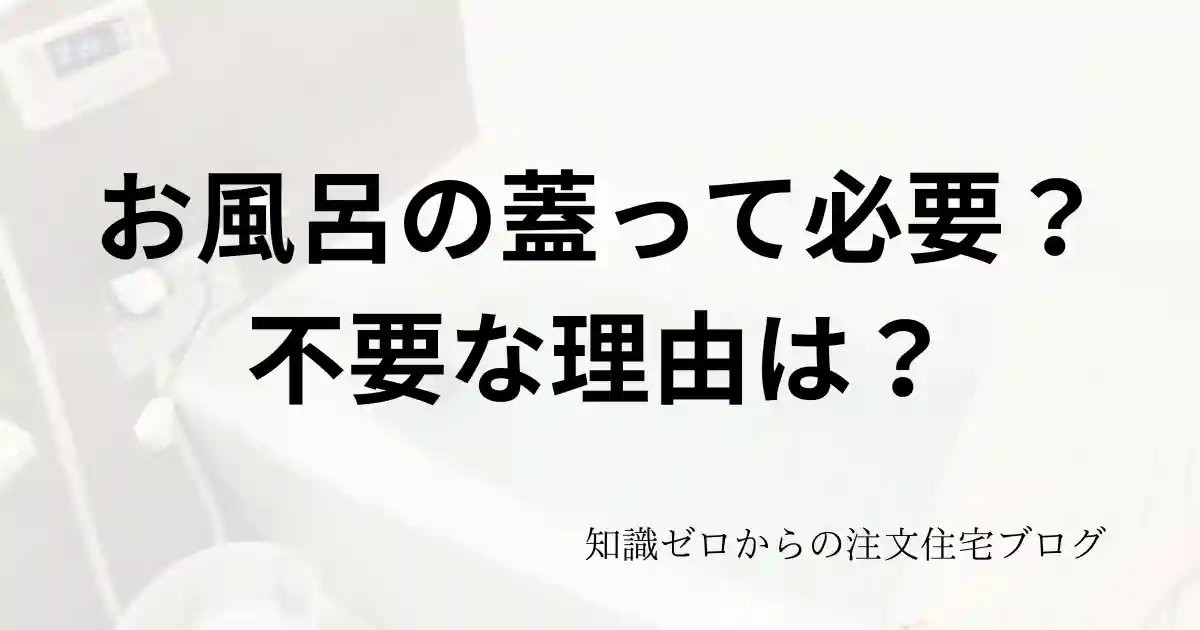

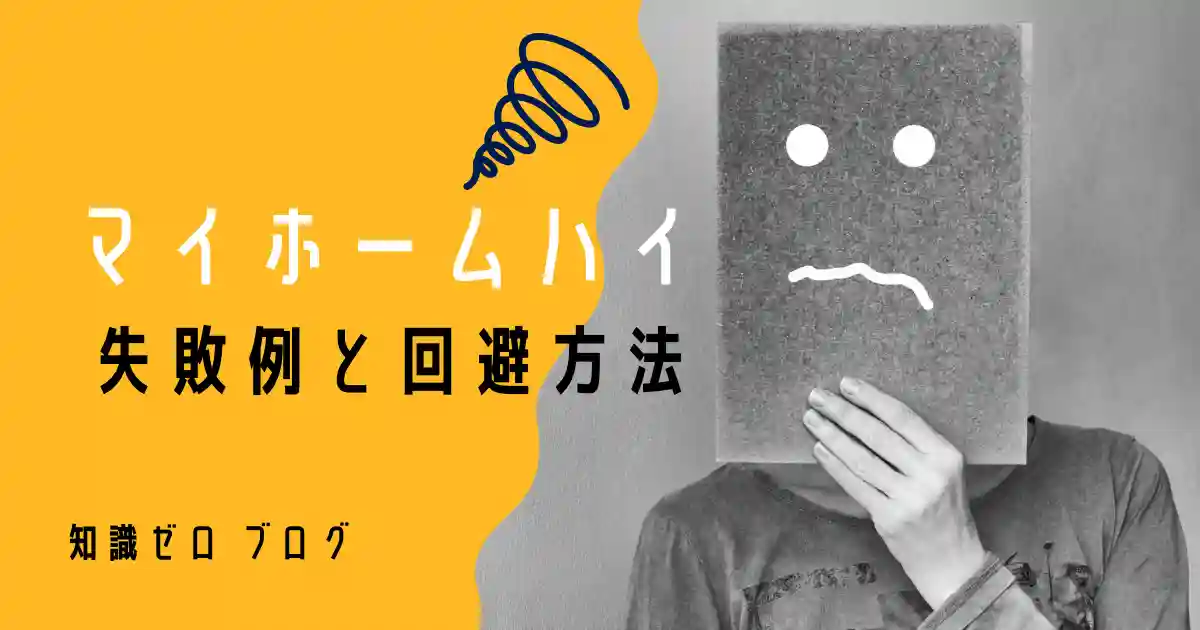

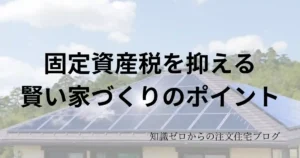
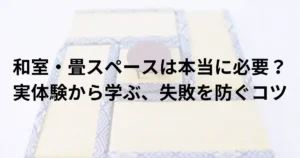
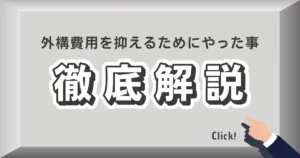
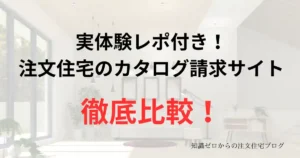
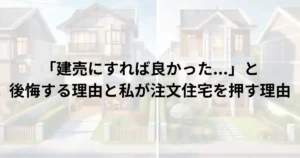
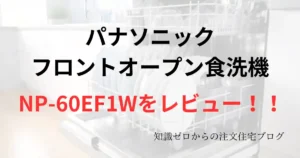
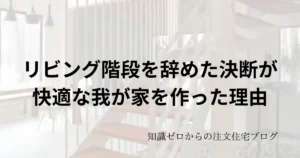
コメント